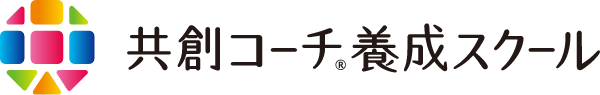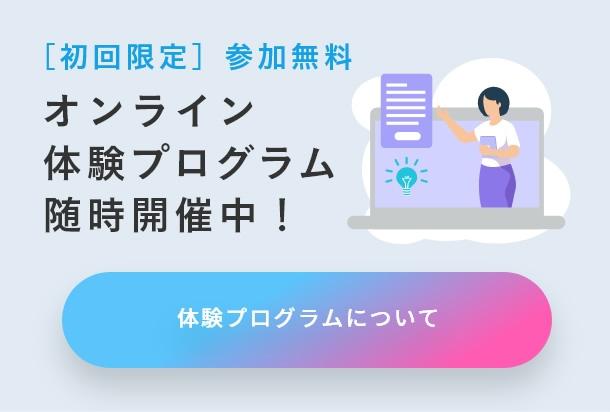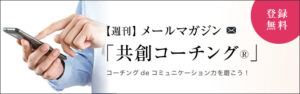なぜ部下のモチベーションは下がるのか?やる気を出させるために重要なコーチングを解説

部下のモチベーションは、業績や職場の雰囲気に大きく影響します。仕事に対する意欲が低下すると、生産性の低下や離職率の増加につながり、組織全体に悪影響を及ぼしかねません。そのため、管理職やリーダーにとって、部下のモチベーションを維持・向上させることは永遠の課題とも言えます。
本記事では、モチベーションの本質から低下の原因、具体的な改善策、さらにコーチングを活用したやる気の引き出し方までを詳しく解説します。部下のやる気を理解し、適切な対応を取るための実践的な知識を早速学んでいきましょう。
▼ 共創コーチ®養成スクールの無料体験の詳細・お申し込みはこちらから▼
モチベーションとは?

モチベーションとは、簡単に言えば「行動を起こす力」や「やる気」のことを指します。仕事におけるモチベーションは、目標達成や成果に向けて主体的に行動する意欲を意味し、個人の生産性や組織全体のパフォーマンスに直結します。
心理学では、モチベーションは内発的動機と外発的動機に分けられており、内発的動機とは、仕事そのものに興味や楽しさを感じること、外発的動機は給与や昇進などの報酬によって生じるやる気です。
管理職としては、部下のモチベーションのタイプを理解し、適切な刺激を与えることが重要です。モチベーションは一時的な気分や感情に左右されやすく、職場環境や人間関係、評価制度などの外的要因が大きく影響します。
そのため、単に「やる気がない」と判断するのではなく、原因を見極めて適切に対応することが求められます。組織としても、社員が自ら行動したくなる環境づくりを整えることが、長期的な成果につながるのです。
なぜ部下のモチベーションは下がるのか?

部下のモチベーション低下には共通する原因があります。まずは原因を整理したチェックリストで確認することが重要です。下記に、一般的に多く見られるモチベーション低下の要因をまとめました。
- 評価やフィードバックが不足している
- 仕事の目的や意義を見失っている
- 成長機会やスキルアップの場がない
- 人間関係や職場環境のストレスが多い
心理的な要因と制度的な要因の両面を考慮することで、改善策を明確化できます。各項目について詳しく見ていきましょう。
評価やフィードバックが不足している
部下は、自分の仕事が組織にどのように貢献しているのかを理解することで、やる気を維持できます。しかし、評価やフィードバックが不足している職場では、部下は自分の努力や成果が認められていないと感じ、モチベーションが低下しやすくなります。特に若手社員や中途採用者は、自分の成長実感がやる気に直結するため、日々のフォローが欠かせません。 評価制度が曖昧であったり、年に一度の人事評価だけでは、部下は努力の方向性が分からず不安を抱えます。結果として、仕事への主体性が低下し、挑戦意欲も失われやすくなります。
対策としては、定期的な1on1面談やプロジェクト単位での振り返りを実施することが効果的です。成果だけでなく、努力や改善点を具体的に伝えることが重要です。
さらに、外部コーチを活用することで、第三者視点の客観的なフィードバックを受けられ、部下の納得感とやる気を高めることが可能です。評価・フィードバックの仕組みを整えることで、部下は自分の成長を実感しやすくなり、仕事に対する主体性や意欲が向上していくでしょう。
仕事の目的や意義を見失っている
部下が自分の仕事の目的や意義を見失してしまうと、日々の業務を単なる作業として捉え、やる気を失いやすくなります。「なぜこの仕事を行うのか」「自分の役割が組織にどう貢献しているのか」を理解できなければ、業務への主体性も低下してしまいます。
こうした事態を避けるために、管理職は、部下に対して業務の背景や目的、組織全体への影響を具体的に説明する必要があります。さらに、目標設定をSMART(具体的・測定可能・達成可能・関連性・期限)に沿って行うことで、部下は自分の役割と成果を実感しやすくなります。
加えて、業務の意味や成果が見える化されることで、部下は自己効力感を高め、自発的に課題解決や改善提案を行うようになるでしょう。組織全体としても、目的や意義の共有を徹底することは、部下のモチベーション維持・向上のために不可欠な施策となるのです。
成長機会やスキルアップの場がない
成長意欲の高い部下にとって、スキルアップや挑戦の機会がない環境はモチベーション低下の大きな要因です。研修や新しい業務への挑戦が不足すると、部下は自分の成長を実感できず、仕事に対する主体性も失われてしまいます。 管理職は、個別面談やキャリア面談を通して、部下の目標や希望に沿った学習・挑戦の場を提供することが不可欠です。
成長機会を整えることで、部下は自己効力感を得やすくなり、主体的に業務に取り組むようになります。長期的には、スキルアップの場を提供することで離職率の低下やエンゲージメント向上にもつながるでしょう。
人間関係や職場環境のストレスが多い
職場の人間関係や環境によるストレスは、モチベーション低下の大きな原因です。上司とのコミュニケーション不足や同僚との対立、長時間労働や過重業務は、部下のやる気を削いでしまいます。
管理職には、チーム内の関係改善や心理的安全性の確保、メンタルヘルス支援を行い、部下が安心して働ける環境を整えることが求められます。外部コーチやカウンセリングを活用すれば、職場のストレス要因を客観的に把握し、効果的な改善策を講じることもできるでしょう。
成功企業の事例では、心理的安全性向上や人間関係改善施策により、離職率が低下し、エンゲージメントが改善されたケースがあります。このように、職場環境の改善は、部下のモチベーション維持・向上のための基盤として非常に重要です。
部下のモチベーションを上げるための方法を解説

部下のモチベーションを向上させるには、心理的アプローチと制度的アプローチの両面から対策を講じることが重要です。心理的アプローチは個人のやる気を引き出す手法で、制度的アプローチは組織としての仕組みを整える方法です。
|
アプローチ |
方法例 |
効果 |
|
心理的 |
1on1面談、コーチング、傾聴・質問・承認など |
個人の主体性ややる気を引き出す |
|
制度的 |
メンター制度、評価制度改善、研修制度、人材開発支援助成金活用など |
組織全体のモチベーション向上 |
現状をしっかり把握する
モチベーション向上の第一歩は、部下の現状を正確に把握することです。定期的な1on1面談やヒアリングを通じて、業務に対する意欲や課題を確認します。
質問は「どの業務にやりがいを感じるか」「どの業務が負担に感じるか」といった具体的な内容にすると、部下も答えやすくなります。
また、アンケートや心理的安全性の評価ツールを活用すれば、客観的なデータを得ることも時には求められます。必要に応じて外部コーチによる第三者視点の診断を取り入れると、社内では見えにくい課題も把握できるでしょう。
このように現状を正確に理解することで、適切な改善策や制度設計が可能になります。
対策を行う
現状分析の結果を踏まえて、具体的な対策を講じることも大切です。具体的な心理的アプローチでは、傾聴・質問・承認といったコーチングスキルを用いて、部下の主体性ややる気を引き出します。
一方で制度的アプローチでは、評価制度改善や研修制度、メンター制度の導入を通じて、成長機会や達成感を提供します。
人材開発支援助成金などの補助金を活用すれば、研修費用や外部コーチ導入のコストを抑えつつ実施できます。重要なのは、施策を一度きりで終わらせず、継続的に効果を確認しながら改善していくことです。
部下のモチベーションを上げるためにはコーチングが重要

ここまでご説明してきたように、部下のモチベーションを高めるには、コーチングは大変有効な手段であることがわかります。コーチングでは、部下の話を丁寧に聞き、質問で自ら考えさせ、成果や努力を承認するという一連のプロセスを通して主体性を引き出します。単なる指示や命令とは異なり、部下が自分で考え行動する力を育てることができるのです。
例えば、あるIT企業ではメンター制度を導入し、新人社員が定期的に先輩と面談する仕組みを設けました。これにより部下は業務やキャリアに対する理解が深まり、離職率は15%から8%に低下しています。また、ある製造業の企業では評価制度を改善し、目標達成のたびにフィードバックを行うことで、部下のモチベーション維持に成功した事例もあります。
つまりコーチングは、制度だけではカバーできない、個々の部下の課題ややる気を引き出す手段として最適解であると言えます。外部コーチ導入型と社内導入型の比較も行い、コストや専門性を考慮しながら、自社に最適な形を選ぶことが成果につながります。総じて、コーチングは部下の主体性向上と組織全体のエンゲージメント改善に直結する施策なのです。
部下のモチベーションを上げるためのコーチングスキル

部下のやる気を引き出すには、コーチングの基本スキルを活用することが不可欠です。代表的なスキルには「傾聴」「質問」「承認」があり、それぞれを日常の業務や面談で意識的に用いることで、部下の主体性やモチベーションを高められます。 スキルを正しく使うことで、部下は自己効力感を得やすくなり、課題に対して自発的に取り組むようになります。そこで、具体的なコーチングスキルの例をご紹介します。
傾聴
傾聴は、部下の話を注意深く聞き、理解しようとする姿勢を示すスキルです。ただ聞くのではなく、言葉だけでなく感情や意図も受け止めることで、部下は「自分の意見や気持ちが尊重されている」と感じられます。
心理的安全性が確保されることで、部下は意見や提案を出しやすくなり、問題解決にも主体的に取り組むようになります。また、傾聴は管理職が部下の課題や強みを正確に把握する手段としても有効です。傾聴を日常的に意識することで、部下との信頼関係が深まり、組織全体のモチベーションにも好影響を与えるでしょう。
質問
質問スキルは、部下に自ら考えさせ答えを見つけさせることで、主体性を育む手法です。指示や命令をするのではなく、「どの方法が最も効果的か」「この課題をどう解決すべきか」と問いかけることがポイントです。
オープンな質問を用いることで、部下は自由に考えを述べ、達成感や成長実感を得やすくなります。また、質問を通して部下の思考過程を理解できるため、管理職は適切なサポートやアドバイスを行いやすくなります。 制度的施策と組み合わせることで、質問スキルの効果を高めることも可能です。例えばメンター制度や評価制度改善の際に、質問を通じて部下の目標設定や課題整理を支援することで、主体性とモチベーションが同時に向上します。
承認
承認は、部下の行動や成果を具体的に認めることで、やる気を高める手法です。成果だけでなく、努力や工夫も評価することが重要です。部下は「自分の取り組みが組織に貢献している」と実感でき、次の行動にも自信を持って取り組めるようになります。
承認は、行動直後に具体的な言葉で伝えると効果が高まります。「今回の提案は○○の点が特に良かった」といった具体性があると、部下は自分の強みを理解し、成長に繋げやすくなるのです。
成功企業の事例でも、承認を日常的に行うことで部下のモチベーション維持とエンゲージメント改善に成功しています。承認は心理的側面だけでなく、組織全体の生産性向上にも寄与する重要なスキルだと言えます。
コーチングスクールをお探しの方は共創コーチングの無料体験へ

部下のモチベーション向上には、傾聴・質問・承認といったコーチングスキルの習得が不可欠です。制度改善やメンター制度との組み合わせで、部下の主体性やエンゲージメントを効果的に高められます。
もし「自社で実践できるコーチングスキルを学びたい」と考えている方は、共創コーチングの無料体験がおすすめです。現場で使える具体的なスキルを学べるだけでなく、部下との信頼関係を築く方法やモチベーションを引き出す実践的なノウハウも体験できます。
まずは無料体験で、自社に合ったコーチングスタイルを確認し、実践に活かしてみましょう。詳しくは下記より公式サイトをご覧ください。
▼ 共創コーチ®養成スクールの無料体験の詳細・お申し込みはこちらから▼