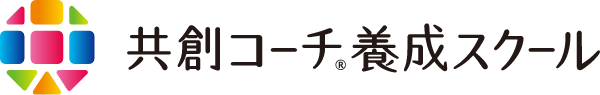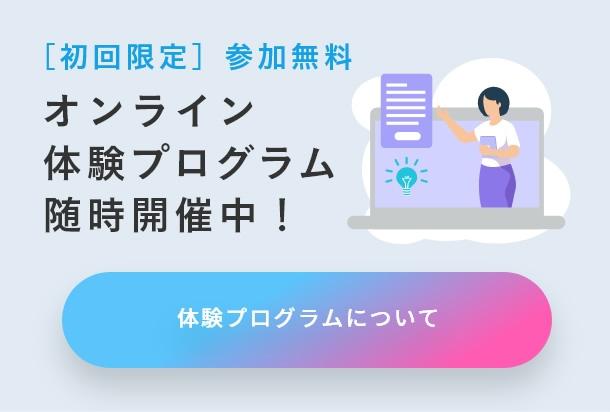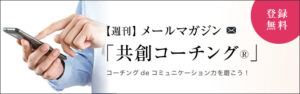コーチング導入の5つのメリットを解説!デメリットや実践するために身につけるべきスキルとは?
 現代のビジネス環境では、従業員の主体性やチームの生産性を高めることが企業成長のカギとなります。その手段のひとつとして多くの企業から注目されているのが「コーチング」です。単なる指示・命令型のマネジメントではなく、個々の能力を引き出すことに重点を置く手法として、全国的に導入が進んでいます。
現代のビジネス環境では、従業員の主体性やチームの生産性を高めることが企業成長のカギとなります。その手段のひとつとして多くの企業から注目されているのが「コーチング」です。単なる指示・命令型のマネジメントではなく、個々の能力を引き出すことに重点を置く手法として、全国的に導入が進んでいます。
本記事では、コーチングの基本から導入によるメリット・デメリット、さらに実践に必要なスキルまで詳しく解説。外部コーチ依頼型と社内導入型の比較や補助金の活用法、実際に成果を上げた企業の事例も紹介します。コーチング導入を検討している企業ご担当者様は、是非最後までお読みください。
▼ 共創コーチ®養成スクールの無料体験の詳細・お申し込みはこちらから▼
コーチングとは?

コーチングとは、個人やチームの目標達成や能力開発を支援するコミュニケーション手法のことです。従来の指示・命令型マネジメントとは異なり、相手の考えや行動を引き出す「対話」を通じて成長を促す点が特徴です。
コーチングはビジネスだけでなく、教育やスポーツの現場でも活用されており、成果を上げる手段として注目されています。具体的には、質問や傾聴、承認を通して相手の思考や感情を整理し、自発的な行動変容を促すことが目的です。
外部の専門コーチを招く「外部コーチ依頼型」と、自社内の管理職や人事担当者がコーチングを行う「社内導入型」があり、企業の規模や目的に応じて選択されます。成功企業の事例を見ると、コーチングを取り入れたチームでは離職率の低下やエンゲージメントの向上が報告されており、企業全体のパフォーマンス改善にもつながっています。
なお、人材開発支援助成金などの補助金を活用することで、コーチングをコストを抑えながら導入することも可能です。
コーチング導入の5つのメリットを解説

コーチングを導入することで得られるメリットは多岐にわたります。特に短期的には部下の主体性やコミュニケーション改善が見込め、長期的にはチームのエンゲージメント向上や離職防止などに効果があります。下記の表で、コーチングのメリットと短期効果・長期効果を整理しました。
|
メリット |
短期効果 |
長期効果 |
|
部下の主体性を引き出せる |
自発的な行動の増加 |
自律型人材の育成 |
|
コミュニケーションの質が向上 |
誤解や摩擦の減少 |
チーム全体の協力体制強化 |
|
チームのエンゲージメントが高まる |
会議や業務への積極参加 |
組織への帰属意識向上 |
|
離職防止・人材定着 |
離職抑止の初期効果 |
長期的な定着率向上 |
|
管理職のマネジメント力強化 |
部下指導力の向上 |
組織運営能力の向上 |
現場でのメリットについて、さらに詳しく見ていきましょう。
①部下の主体性を引き出せる
コーチング最大のメリットの一つは、部下の主体性を引き出せることです。従来の上司からの指示命令型マネジメントでは、部下は指示に従うだけになりがちですが、コーチングでは「考える力」を育むことに重点を置きます。
具体的には、部下の課題や悩みに対して質問を通じて自ら答えを導くプロセスをサポートします。その結果、部下は自発的に行動するようになり、業務改善や新しい提案が自然と生まれやすくなるのです。
また、主体性が育つことで、チーム全体の効率や生産性も向上します。成功企業では、この主体性向上によりプロジェクトのスピードが上がった事例も見られました。
外部コーチ依頼型と社内導入型を比較すると、外部コーチは客観的な視点で部下の主体性を引き出せます。一方で社内導入型は日常業務と連動した継続的な指導が可能であり、組織の状況に応じて選択することが望ましいと言えるでしょう。
②コミュニケーションの質が向上する
コーチングでは、部下との対話が中心となるため、自然とコミュニケーションの質が向上します。具体的には、上司が傾聴力を高め、部下の意見や気持ちをしっかり受け止めることで、誤解や摩擦が減少する効果が期待できるでしょう。
また、適切な承認やフィードバックを行うことで信頼関係が築かれ、業務のやり取りもスムーズになります。結果として、部下は自分の意見を遠慮なく表現できるようになり、チーム全体の情報共有や意思決定の質が高まるのです。
外部コーチを活用する場合は、中立的立場からコミュニケーション改善を促すことができ、社内導入型の場合は日常業務の中で自然に対話スキルが向上する点がメリットです。継続的なコーチングによって、組織文化そのものが「オープンな対話」を重視する方向へ変化していくのです。
③チームのエンゲージメントが高まる
コーチングを導入すると、チームのエンゲージメントも向上します。エンゲージメントとは、仕事への熱意や組織への帰属意識を指し、従業員のパフォーマンスや定着率に直結する重要な要素です。部下が自分の意見やアイデアを尊重される環境では、やる気やモチベーションが自然と高まります。
企業での実践例としては、コーチングを通じて定期的に部下との1on1を行った結果、離職率が低下し、チームの自主的な改善提案が増えたケースがありました。また、エンゲージメントが高まることで、チーム全体の生産性や顧客満足度にも好影響が見られます。
外部コーチ型と社内導入型のいずれも効果はありますが、継続性を重視する場合は社内導入型の方が長期的なメリットを享受しやすいとされています。
④離職防止や人材定着に効果がある
部下の主体性やチームのエンゲージメントが向上すると、自然と離職防止や人材定着にもつながります。従業員は自分の成長が実感でき、組織への信頼感が高まるため、離職意向が低下します。
実際にコーチングを導入した企業では、離職率が1年で10%低下した事例も報告されていました。外部コーチ依頼型の場合、短期的に成果を出すことができる一方、社内導入型は長期的な育成・定着に向いています。企業の状況や目的に応じて導入方法を選ぶことが重要です。
⑤管理職のマネジメント力が強化される
コーチングは管理職自身のスキル向上にもつながります。部下の話を傾聴し、本質を引き出す質問を行う過程で、管理職のコミュニケーション能力や問題解決能力が自然に向上します。結果として、管理職は単なる指示者ではなく、部下の成長を支援するリーダーとしての役割を果たせるようになるのです。
また、部下の状態を的確に把握し、適切な承認やフィードバックを行うスキルが身につくことで、チーム全体のモチベーション維持や業務改善にもつながります。成功企業の事例でも、管理職のコーチングスキル向上が従業員のパフォーマンス改善と直結していることが確認されています。管理職の成長が組織全体の成長に直結するため、コーチングは企業の重要な投資対象といえるでしょう。
コーチング導入のデメリットを解説

ご説明してきたようにコーチングには多くのメリットがあります。しかし一方で、導入する際にはいくつかの注意点やデメリットも存在します。大前提として、組織全体で効果を出すためには時間やコストがかかることが少なくありません。
ここからは、こうしたコーチング導入における主なデメリットについて詳しく解説します。事前にリスクを把握することで、より効果的にコーチングを活用できるようになるでしょう。
成果が現れるまで一定の期間を要する
コーチングは短期的な指示や教育と異なり、部下の考え方や行動の習慣を変えるプロセスを重視します。そのため、成果が目に見える形で現れるまでには一定の期間が必要です。特に社内導入型の場合、管理職がコーチングスキルを習得し、それを部下に実践するまでに数か月以上かかることもあります。
この期間中は上司も部下も変化に慣れるまで試行錯誤が続くため、短期的な成果だけを期待していると効果が感じにくく、導入へのモチベーションが低下するリスクを避けられないでしょう。外部コーチ型であっても、部下一人ひとりに適切な質問や承認を行い、習慣化するまでには時間を要します。
したがって、コーチング導入では長期的な視点を持ち、段階的に成果を確認しながら進めることが重要です。
一人のコーチが同時に多人数を指導するのは難しい
コーチングは本来、個々の部下の思考や行動を引き出すための個別対応が基本です。そのため、一人のコーチが多人数を同時に指導する場合、どうしても効果の質が落ちる可能性があります。
外部コーチを依頼する場合、限られた時間の中で全員に均等なサポートを行うのは難しく、面談の間隔が空きすぎたり、フォローアップが不十分になるケースがあります。部下の成長スピードに差が生まれたり、チーム内で不満が出ることも少なくありません。
一方、社内導入型の場合でも、管理職が日常業務と並行して全員のコーチングを行うには時間的制約があります。忙しい業務の中で個別面談を実施することが難しくなり、部下の状況把握や指導の質が低下するリスクもあります。
こうした課題を回避するには、対象人数を段階的に分けて実施したり、グループディスカッションやワークショップ形式を併用するなどの工夫が必要です。オンラインツールや1on1面談の定期スケジュール化を活用することで、効率的に多人数指導を行えます。ポイントは、人数を無理に増やさず、質を優先して段階的に実施することです。
コーチの力量やスタイルによって効果に差が出る
コーチングの効果は、指導するコーチ自身の力量や経験、そしてスタイルに大きく左右されます。コーチが十分なスキルを持たない場合、部下の本音や課題を引き出せず、期待した成果が得られないことがあります。
承認やフィードバックが不十分だと、部下のモチベーションが低下し、行動変容につながらないケースもあるでしょう。コーチのスタイルによっては、部下に圧力を感じさせてしまい、逆に主体性を阻害する可能性もあります。
外部コーチ型の場合は、専門知識や経験豊富なコーチを選ぶことが重要で、短期間でも高い成果が期待できる一方で、社内導入型では管理職がコーチングスキルを習得し、継続的に実践する必要があります。
同じ組織内でもコーチのスタイルに差があると、部下ごとに成長スピードやモチベーションにばらつきが生まれかねません。このため、導入時には研修やスキルチェックを行い、コーチ間で一定の質を担保することが重要です。ポイントは、単にコーチングを導入するだけでなく、コーチ自身の育成や質の管理まで含めて計画することです。
コーチングを実践するために身につけるべきスキル

コーチングを効果的に実践するためには、単に知識を知っているだけでは不十分です。部下やチームの成長を引き出すには、実践的なスキルを身につけることが不可欠です。
コーチングは短期的な指導法ではなく、長期的な成長を促す手法であるため、継続的にスキルを高める姿勢が求められます。ここからは、実践に必須となる主要スキルを詳しく解説します。
ストローク
ストロークとは、相手の存在や行動に対して「あなたを見ている」「関心を持っている」と伝える行為を指します。心理学的な観点からも、人はストロークを受け取ることで安心感や自己肯定感を高めることができます。
コーチングでは、小さな行動や努力をその都度ストロークとして返すことが重要です。例えば「会議での説明がわかりやすかったよ」と具体的に伝えることで、部下は「自分は貢献できている」と実感できます。肯定的なストロークはもちろん、改善点を建設的に指摘することも、学習意欲を引き出す効果があります。
傾聴力
傾聴力とは、部下の話を遮らず最後まで聞き、内容だけでなく感情や意図も正確に理解する能力です。コーチングでは、部下が自分の考えや悩みを安心して話せる環境を作ることが非常に重要であり、傾聴力はその基盤となります。
傾聴力が高いコーチは、部下が自分の思考や感情を言語化しやすくなるため、本質的な課題や改善点を引き出せるのです。また、部下は自分の意見が受け止められていると感じることで信頼感を深め、主体的な行動を促されやすくなるのです。
実際の企業事例では、管理職が部下の話をじっくり聞く姿勢を徹底することで、部下が自己解決能力を身につけ、改善提案ができるようになったというケースがあります。傾聴力の習得には時間がかかりますが、練習やフィードバックを重ねることで確実に向上するでしょう。重要なのは、聞くことに集中し、判断やアドバイスをすぐに挟まず、まずは部下の思考や感情を受け止めることです。
相手を理解・共感する姿勢
コーチングにおいて、相手を理解し共感する姿勢は非常に重要です。単に話を聞くのではなく、部下の立場や気持ちに寄り添い、考えや感情を正しく理解することで、信頼関係を構築できます。
具体的には、部下が話している内容だけでなく、その背景にある思いや感情に注目し、言葉や態度で理解を示すことが求められます。例えば、「それは大変だったね」といった共感の言葉を添えつつ、非言語的な反応でも理解を伝えることが効果的です。
成功事例として、共感力を重視したコーチングを導入した企業では、部下の自主的な改善提案や積極的な業務参加が増加し、チーム全体のパフォーマンス向上や離職率低下にもつながっています。
共感力も一朝一夕で身につくものではなく、意識的に練習し、部下の反応を観察しながら改善することで身につくものです。コーチとしての成長が、部下の成長にも直結するスキルと言えるでしょう。
本質を引き出す質問力
コーチングにおいて質問力は、部下が自ら考え、課題の本質を理解し、主体的に行動できるように導くための重要なスキルです。単に答えを教えるのではなく、相手の思考を引き出す質問を投げかけることで、部下は自分で解決策を見つける力を養うことができます。
効果的な質問の例としては、「なぜその結果になったと思いますか?」「次にどのようなアプローチを試しますか?」など、具体的で思考を深める内容が挙げられます。あいまいな質問や答えやすい質問ばかりでは、部下の主体性や創造性を引き出すことはできません。
質問力は日常業務の中で磨くことが可能です。1on1面談や業務振り返りの際に、部下の発言に注目して掘り下げる質問を意識的に行うことで、自然にスキルを磨いていけます。ポイントは、答えを急がず、部下が考える時間をしっかり与え、引き出す姿勢を持つことです。質問力を高めることで、部下の成長速度を加速させ、チーム全体のパフォーマンス向上にもつながるでしょう。
相手を認めて励ます承認力
承認力とは、部下の行動や成果を適切に評価し、励ます力のことです。単なる褒め言葉ではなく「なぜその行動が価値あるのか」を明確に伝えることが、モチベーション向上につながります。
承認の対象は成果だけでなく、努力や改善のプロセスにも及びます。例えば「締切に間に合わせる工夫をしてくれたね」と伝えることで、部下は自信を持ち、さらなる挑戦に意欲的になれます。
また、承認は口頭だけでなく、メールやチャットなどあらゆる場面で可能です。適切なタイミングで承認を行うことが、部下のやる気と自主性を持続させる源となります。
コーチングの導入方法

コーチングを導入する際には、企業の規模や目的に応じた方法を選ぶことが重要です。これまでも触れてきましたが、大きく分けた場合一般的に「外部コーチ依頼型」と「社内導入型」の2種類があります。
外部コーチ依頼型は、専門的な知識と経験を持つコーチを招き、短期間で部下やチームのスキル向上を図る方法です。初めてコーチングを導入する場合や、特定の課題解決を急ぐ場合に有効です。
一方、社内導入型は管理職やリーダーがコーチングスキルを習得し、日常的に部下への指導を行う方法です。長期的に組織文化として定着させたい場合や、継続的な人材育成を目指す場合に適しています。
導入の際には、人材開発支援助成金などの補助金制度を活用することで、コストを抑えながら始めることも可能です。また、初めて導入する企業は小規模なトライアルを実施し、効果や課題を確認してから本格展開するのがおすすめです。
対象人数や頻度を調整することで、コーチの負荷を抑えつつ、全員が効果的な指導を受けられる体制を整えられます。導入計画をしっかり立てることで、短期的な成果だけでなく、長期的なチームの成長や定着にもつなげることができるでしょう。
コーチング導入は無料体験から始めよう

本記事では、コーチング導入にかかわるメリットだけでなくデメリットについても解説しました。どの企業にコーチングをお願いするか、なかなか決められない方も多いでしょう。
そんな企業ご担当者様におすすめなのが、共創コーチングの体験セミナーです。体験セミナーでは、コーチングの自社導入に向けた具体的なイメージをつかむことができ、部下の主体性向上やチームのエンゲージメント改善に直結するスキルを体験いただけます。
共創コーチングでは、受講生一人一人にとってコーチングの学びが人生を意義深くするための成長・発達の機会となるように、経験学習のセオリーを軸に学習を設計しています。
まずは無料体験で、コーチングの効果を実感し、部下との信頼関係やチーム全体の成長につなげてみませんか。
▼ 共創コーチ®養成スクールの無料体験の詳細・お申し込みはこちらから▼